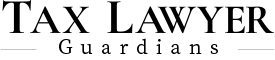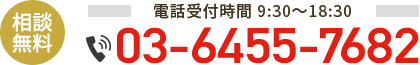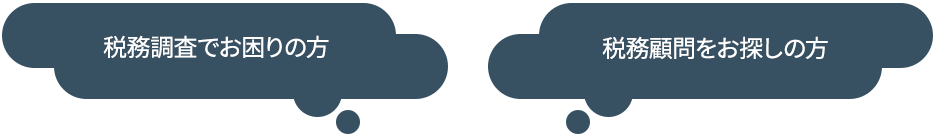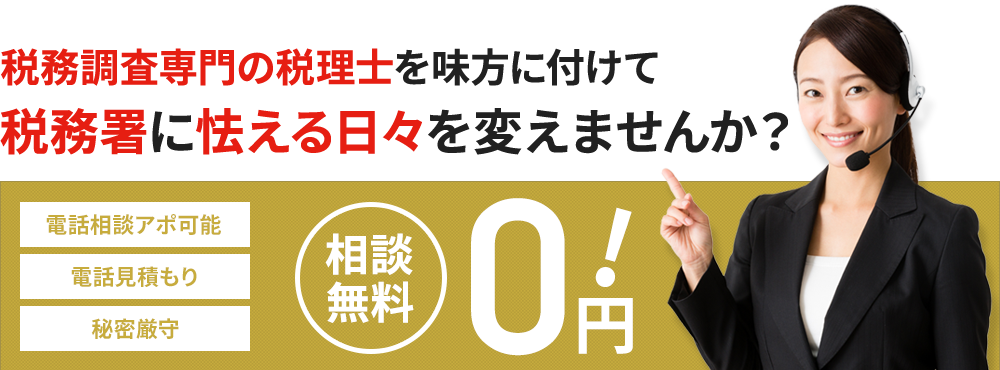税務調査が入り、税務署から指摘された内容に疑義が残る場合、納税者が是正を求めることができる最終的な切り札になるのが税務訴訟です。
納税者には適正な税金を納める義務がある一方で、万が一課税処分に誤りがあった場合には見直しを求める正当な権利も持っています。
税務訴訟で勝訴することは簡単ではなく、しかも訴訟対応に相応の時間と費用がかかります。しかし、客観的な根拠と証拠資料を揃えることで勝訴した事例もあります。
そこで、本記事では税務訴訟の目的や流れ、納税者が勝訴した事例などについて解説します。
税務訴訟とは?

税務訴訟とは、税務調査の結果として税務署が下した課税処分に、最終的に司法の場で白黒をつけるための手段です。
税務訴訟には様々な種類がありますが、大半のケースは課税処分の取り消しを求める取消訴訟です。
納税者は課税処分の取り消しを求める場合は、税務調査後、すぐに裁判所に税務訴訟を起こすことができません。
次の流れのように、まず行政機関に処分の見直しを求めることが定められており、それでも疑義が残る場合に最終手段として税務訴訟を提起できます(国税通則法第115条)。
税務訴訟を起こすまでの流れ
| 更正処分 | 税務調査の結果、納税者が税務署の指摘に疑義があり、修正申告に応じないことがある。その場合、税務署長は「申告内容に誤りがある」として、納税額を強制的に決定することができるが、これを更正処分という。 |
| 不服申し立て | 納税者は、国税不服審判所という機関に対して「更正処分の内容に誤認があるので、もう1回審査してください」と、不服を申し立てる(審査請求)。 |
| 裁決 | 国税不服審判所が、税務署の処分が妥当かどうかを判断する。 |
| 税務訴訟 | 不当な理由で青色申告の承認取り消し処分を受けたり、推計課税(明確な書類等がない場合に特定の割合を使用して課税)が行われたりした場合。 |
| 不公平な課税処分 | 【裁決が出た場合】裁決の結果に対して、納税者は法的な観点で客観的な疑問が残る場合、裁判所に6ヶ月以内に税務訴訟を起こすことができる。 【裁決が出ない場合】審査請求から3ヶ月経過しても裁決が出ない場合に、納税者は税務訴訟を起こすことができる。 |
なお、税務調査の不服申し立てについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
→関連記事:「税務調査の不服申し立て|税務署の指摘に不服がある場合の対応方法
税務訴訟の大まかな流れ

審査請求の裁決に疑義が残る場合、もしくは裁決がない場合は、次の流れで税務訴訟に進みます。税務訴訟を提起してから第一審判決が言い渡されるまでは1年半~2年程度かかると言われています。
訴状の提出
税務訴訟に限らず、民事訴訟は、納税者(原告)が裁判所に訴状を提出することから始まります。税務訴訟の訴状では、課税処分を取り消してほしい旨と、なぜ取り消すべきなのか(事実関係や法的根拠)を明確に記載します。
さらに、訴状と併せて、原告の主張を裏付ける証拠書類も裁判所に提出します。証拠書類の内容が、その後の税務訴訟の方向性を決定づけるため、極力正確な証拠書類を網羅して提出しなければいけません。
答弁書の提出
訴状が裁判所から国(被告)に送達されると、国側はそれに対する反論を示した答弁書を提出します。答弁書では、通常、納税者側の主張を否認し、「行った課税処分は適法かつ正当である」という国側の基本的な立場が示されます。
納税者は、答弁書によって国がどのように課税処分の正当性を主張してくるのかを具体的に知ることができます。
口頭弁論(準備書面・証拠の提出)
口頭弁論とは、法廷において裁判官の指揮のもとで原告と被告の双方が主張を述べて、証拠を提出する手続きです。「口頭」とありますが、実際には交互に準備書面を裁判所に提出して、反論を重ねていくプロセスが中心です。
口頭弁論は何回も繰り返すことがあり、1年以上の期間を要することも珍しくありません。
証人尋問
証人尋問とは、裁判で事実を明らかにするため、証人に直接質問をして証言を得る手続きで、テレビドラマでよく見られるシーンです。証人尋問は、書面での主張と証拠が出尽くし、争点が固まった段階で行われます。
証人尋問は事前に召喚状が届くので、徹底した準備を行い、これまで主張してきた事実関係を自身の言葉で裏付けるようにします。事前に弁護士とリハーサルを行うことも大切です。
判決
すべての審理が終わると、裁判所は第一審判決を言い渡します。判決に不服がある場合、判決書の送達から2週間以内に控訴することができ、控訴審の判断にも不服があれば最高裁判所に上告することができます。
税務訴訟で勝訴した3つの事例

税務訴訟で勝訴し、審査請求の裁決を覆すことは決して簡単ではありません。
国税庁「令和6年度における訴訟」の概要によれば、令和6年度の税務訴訟の終結件数168件に対して、納税者側が勝訴したのはわずか8件、割合にして4.8%です。
しかし、勝訴率が低いとはいえ、国税不服審判所の採決を覆した事例があることも事実です。
特に税務訴訟の経験が豊富な弁護士や税理士と連携して、客観的な証拠を的確に集めることができれば、決して勝訴は不可能ではありません。そこで、税務訴訟で勝訴した事例を紹介します。
シンガポール・レンタルオフィス事件
日本の納税者がシンガポールに設立した子会社が、タックスヘイブン対策税制の適用対象となるかが争われた税務訴訟です。タックスヘイブン税制とは、税金が低い国を利用した日本での課税逃れを防ぐ税制のことです。
その子会社は、レンタルオフィスの一角に机とパソコンを置き、非常勤の取締役と派遣社員で小規模な卸売業を行っていました。しかし、税務署は「事業の実体がないペーパーカンパニーである」と判断して、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たさないとして、その所得を日本の親会社の所得と合算して課税しました。
一方、納税者側は、小規模なオフィスであっても、そこで事業活動が行われている実態を、証拠書類で丹念に立証しました。その結果、裁判所は納税者の主張を全面的に認め、課税処分を取り消しました。
ワールドファミリー事件
ワールドファミリー事件は、移転価格税制が争点となった税務訴訟です。移転価格税制とは、海外の関連会社間との取引価格を適正に設定して、企業の所得移転や租税回避を防止するルールです。
ディズニーの幼児向け英語教材を販売する日本法人が、教材を海外の関連会社から仕入れていました。税務署は、「日本法人が海外の関連会社に適正価格よりも高い金額を支払うことで、国内の利益を海外に移転している」と判断し、移転価格税制に基づき課税処分を行いました。
しかし、企業側は、「知名度のあるディズニーのブランドを持つ商品と、一般的な教材と価格を比較することはおかしい」と主張します。裁判所は、無形資産の価値を立証した納税者の主張を認め、課税処分を取り消しました。
ユニバーサルミュージック事件
ユニバーサルミュージックの日本法人が、グループ内の組織再編の一環として、海外の関連会社から多額の資金を借り入れました。そして、支払利息を損金計上し、法人税額を圧縮しました。
税務署は、「事業目的ではなく、国内の税金を不当に減らすために行われた人為的な取引」と判断して、損金計上を認めず、追徴課税しました。一方、納税者側は、この借入がグループ全体の効率化を目指した大規模な組織再編計画の一部であったと主張し、税務訴訟を起こします。
裁判所は、「大規模な組織再編計画という経済的合理性があり、意図的に法人税を圧縮したとは言えない」と判断して、課税処分を取り消しました。
【まとめ】税務訴訟は課税処分の誤りを是正する最後の手段
税務訴訟は、税務署の課税処分の誤りを是正できる、納税者に認められた正当な権利です。勝訴は簡単ではありませんが、客観的な証拠を集めることができれば、勝訴の可能性はあります。
当税理士法人TAX LAWYERは、税務訴訟の経験が豊富な弁護士と連携して、訴訟の準備から裁判所での弁護まで一貫したサービスを提供しています。税務訴訟を検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。